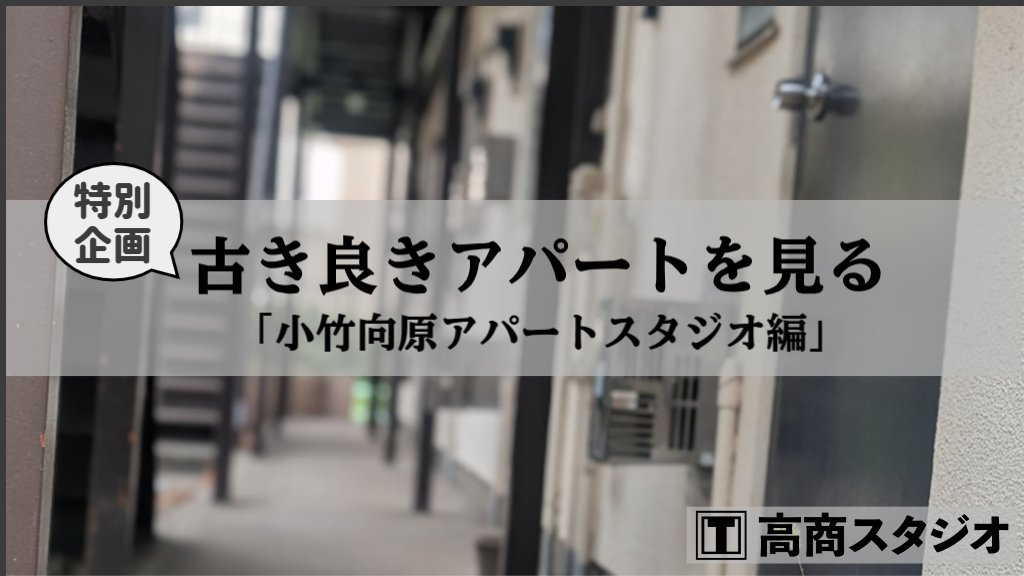毎度おなじみ流浪のブログ、高商ブログでございます🕶
今回は弊社でも人気の高い小竹向原アパートスタジオをいつもとは違う視点でゆるっと見ていきましょう。

小竹向原アパートスタジオ外観
ドラマ撮影で人気のスタジオ「小竹向原アパートスタジオ」
練馬区小竹町1丁目にひっそりと佇むこちらのアパート。
1970年代後半~1980年頃に建てられた築45年以上のアパート丸ごと一棟貸しのスタジオとなっています。木造二階建て101~206号室の全10戸で104、204は欠番です。4を忌避する風習にも趣を感じます。建物名は小竹ハイムです、古臭い〇〇荘から西洋風のハイムやハイツ、コーポが流行した時代でしょうか。
まさに平凡なよく見るアパートですよね。かなりボロ、いや侘び寂びを感じさせます。
よく見るアパートが建てられた時代背景
戦後の日本は深刻な住宅不足に悩まされていました。
その後の高度経済成長期においても都市部への人口の大量流入、都心の過密化や所得向上による郊外への居住地域の拡大、これらに対応するために全国で低コストな住宅が大量に供給されました。
特に1951年成立の公営住宅法などに基づき、日本住宅公団(現:UR)や地方住宅供給公社(JKK)が低・中所得層向けの住宅地開発を行い、国や自治体主導で日本全国の都市近郊に画一的な借家やニュータウン・団地が造成されました。人々はそこを新たな”ふるさと”としました。
(この時代に欧州共同体が作成した内部資料で日本の住宅は”ウサギ小屋”と揶揄されたのは有名な話ですよね…)
民間でも安価な住宅が大量生産される中で、小竹ハイムの様な木造・鉄骨造のアパートの場合は建築基準法における耐火性や用途地域による規制、コスト等の都合で二階建ての似通った見た目と構造になってしまうのです。

画一的なアパートが並ぶ公営団地。独特の無機質さとノスタルジー、社会主義的な雰囲気がマニアに刺さる風景です。
住宅もまた日本の大量生産・大量消費時代のその流れの中にあったのです。
小竹ハイムが建てられたのは時代的には高度経済成長期の終わりでバブル直前の頃、都心の地価は上昇し郊外化が進んでいた時期です。(最近はずっと都心回帰の傾向ですよね)
きっと未来のある若者もたくさん住んでいたのではないしょうか。
アパートの外観をじっくりと見ていく

古びた外観のディティールを見てみる
外観で特徴的なのはこのシンメトリーに配置された外階段。この階段と通路の縦柵、各部屋の窓の面格子が統一感のあるデザインとなっています。(外観撮影OKなので階段を使った芝居もできます!)

木製の面格子
この面格子もアルミ製ではなく木製です!時代を感じます。
今では既製品のアルミ格子をポンと取り付けるだけだと思われますが、これは当時の大工さんが木材を刻んで手作業で作ったのでしょうか。
(余談ですが近年の闇バイト絡みの事件の増加から防犯用面格子が品薄となっているらしいです。怖いです。)

風呂入ってるなってバレバレです
もう一つの小さい窓はお風呂のルーバー窓になっています。最近ではルーバー窓の採用も減っていますよね、主に防犯と断熱性の低さのためです。
その奥にはオシャレな格子が取り付けられています。
コスト的な制限と合理性の中でもデザインセンスを感じさせるポイントです。

外観裏手。こちらから室内に照明を入れることも可能。
裏はこうなっています、プライバシーなんてありません。
なつかしさ漂う室内
各部屋は4畳半と6畳の2Kとなっています、古いアパートでは定番の間取りです。
炊事場は玄関すぐに配置し、リビングやダイニングなどの部屋ごとの決まった用途の概念は無く、畳の部屋が襖で仕切られただけの空間は伝統的な日本の住宅の構造と言えるのではないでしょうか。

101号室。2Kとはいえキッチンは広めでダイニングとしても使えそう。

101号室。手前が4畳半、奥が6畳。
101号は空き部屋となっており、引っ越しのシチュエーションや待機部屋として使われたりします。
その他の部屋はそれぞれ違ったテイストのインテリアを用意しております。
また、102・103号室と201号室はモダンにリフォームされ、外観とは全く異なる世界になっております。気になる方はこちらをご覧ください→小竹向原アパートスタジオ
水回りには時代と文化レベルが反映される

105号室のおトイレは新しめでウォシュレット付き。トイレの使えないお部屋もありますのでご注意ください。

こちらは206号室
風呂とトイレは別で、トイレは全て洋式です。もちろん長年の間に各部屋でリフォームや取り換えがあったはずですが、年代的には建築当時から水洗洋式のトイレだったのではないかと思います。日本における水洗洋式トイレの普及は60年代以降に日本住宅公団が公営住宅へ採用したことと、東京オリンピックが契機となったそうです。今では和式とか汲み取り式なんてめったにお目にかかれなくなりましたよね。

105号室。水色のタイル張りに、花柄のステンレス浴槽がレトロです。左にあるのがバランス釜。

206号室。こちらは床だけTOTOのバスパネルが入っています。タイル床が水漏れなど起こして改修したのでしょうか。
風呂に関してはタイル張りのいわゆる在来工法の物となっています。これもタイル職人が手作業で貼ったのでしょう。
在来工法に対して現在では主流のユニットバス(ユニットバスとは浴室全体を工場で生産し現地で組み立てる工法で工期短縮とコストカットが可能。浴槽・トイレ・洗面台が一体になったものは3点ユニットと呼ばれます、日本初のユニットバスはこの3点タイプ)もやはり東京オリンピックが契機で普及が始まったものと言われています。ただ洋式便器の普及よりは遅かったようです。確かに自分の実家も便器は洋式で風呂はかつてはタイル張りでした。ウォシュレットも途中から付いた記憶があります。
給湯器はバランス釜と言われるものでこれも今では見かけませんよね、現役で使用可能ですが動作の保証はいたしかねます。撮影で使うことはほとんどないですね。
タイル貼りで狭くて深い、とても快適なお風呂とは言えませんが、それでも湯船に浸かりたいのが日本人でしょう。
また、時代を考えると風呂無しトイレ共用というアパートもまだ珍しくなかった時代、各戸に炊事場と風呂トイレがあるアパートは十分文化的だったのではないでしょうか。
高度経済成長期に近畿地方で大量に建てられた低所得層向け集合住宅である”文化住宅”もトイレと炊事場が戸別にあった事からそう呼ばれました。水回りの快適性とクオリティは生活レベルに大きく関わりますよね。

大阪市内の文化住宅。現代的なアパートの先駆けではないでしょうか。
ちなみに浴槽と洗面台とトイレが一体となった3点ユニットバスが普及するのは1980年以降のバブル期の事で、小竹ハイムが建てられた後の流行です。
現在でも都市部の集合住宅やホテルでは現役です。新築での採用は減っていますが当時は西洋風で最先端で合理的なものとして受け入れられました。時代と共に人々の生活様式は変化し、住宅も変化し続けるのでしょう。
(僕の住むマンションも3点ユニットです、ホテルっぽいし住めば都です)

参考:3点ユニットバス
キッチンに関しても各部屋で改修が繰り返され年代が違うものが入っていますが、この206号室の物が特に古いように思います。関厨房という会社の製品のようです。ガステーブルとノーリツの瞬間湯沸かし器が懐かしい雰囲気です。この小さなキッチンと言い、4畳半の薄暗い和室と言い、南こうせつの歌がピッタリな世界観を醸し出していますよね。

206号室キッチン

こちらは101号室。さすがに汚いですが、これはこれで需要があるのか?
住宅は時代を映し、人々の生活とドラマの舞台です。
長いのでこのくらいで、いかがでしょうか。
なんてことのないアパートについてウンチクを垂れるだけのふざけた内容でしたが、こんなボロアパートでもその時代の情勢を表していますし、たくさんの人が住んだ歴史があるのです。
こういった物件は時間と共に失われていきますが、そこにはきっと誰にも知られないドラマがあったはずです。このスタジオに入る度にその記憶が充満し、染みついているのを感じます(ただのホコリとヤニの匂いかもしれません)。
この本物の時間が作り出す”味”は作り物やセットでは再現不可能なものです。これこそがこのスタジオが求められる理由でしょう。
あなたの町にもきっとある古びたマンションやアパート、そこにはたくさんの本物のドラマがあるのです。
今回取り上げた「小竹向原アパートスタジオ」の詳細はコチラ